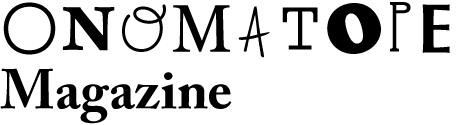〜成安造形大学 総合領域について〜
 Photo:Motohiro Okumura
Photo:Motohiro Okumura
成安造形大学の「総合領域」は、その名のとおりデザインを総合的に考えます。あらゆることをデザインという観点から捉え、活かし、実行していくことを身につけていくことを目指します。私たちはこれを「デザイン思考」と呼びたいと思います。
総合領域では、「デザイン思考」とその具体的な基礎を学ぶ領域独自の授業を軸にしながら、イラストレーション領域、美術領域、情報デザイン領域、空間デザイン領域、地域実践領域という他の5領域の授業も受けることができるので、さまざまなスキル、知識を幅広くプラスすることができます。またプロジェクト授業も積極的に履修し、実践力を身につけていきます。
領域独自の専門科目では、冊子の編集やマーケティング調査、コンセプトメイキング、プランニング、ブランド計画、デザインマネジメントなどを行う授業があり、個人制作だけではなく、グループ制作(グループワーク)もたくさん行っているのが特徴です。
一人の力で実現できることには限界があります。大きな企画をより広い社会に発信していくためには、多くの専門家の力を結集する必要があります。そこで大切なのは、自分の考えを他人に伝える力や、相手の考えを聞き取る力、また、それらをまとめあげる力=「コミュニケーション力」です。総合領域では、グループワークを通してコミュニケーション力を養い、バラバラなパーツをひとつにまとめあげ、活かしあうような、統合的問題解決力を身につけていきます。そのほかにも、フィールドワーク形式の授業も用意されています。本やネットで調べるだけでなく直接に現場に関わることが、集めた情報を活かす基本となるからです。カリキュラムの仕組み、授業の例は、>>こちらをご覧ください。
成安造形大学の「地域連携推進センター」は各種プロジェクトの運営を行う専門部署で、社会との窓口として学生や教員とのパイプ役を果たしています。多くのプロジェクトは「プロジェクト科目」として授業単位化されています。総合領域では実践力を重視し、プロジェクト科目を履修することを積極的に推奨し、必修科目に代わる卒業要件の単位として認められています。また、プロジェクト授業のほかにも「学生クリエイター」などの制度もあります。卒業にむけた学びのひとつとして積極的に参加してください。
基本的には、一人ひとりの目的や目標に合わせて、何を学ぶかを自由な組み合わせで考えていきます。しかし、これは「好きなことだけをすればいい」ということでは決してありません。好き嫌いだけで学びを組み立てると偏った能力しか身につきません。食わず嫌いをせずに幅広く、バランスの取れた学び方を教員との面談などを通して考えていきます。
また、すべての科目に受講定員が設定されています。科目によっては希望者数が受講定員を超え、受講できないことがあります。その場合は希望内容を再調査したうえで調整を行います。受講条件(基本的に自分より上の学年の授業は取れない等)もあるので、経験豊かな教員やスタッフのアドバイスを受け、1年後、2年後のことも考えながら履修計画を立てる必要があります。
この記事に関してのお問い合わせは.>>こちら
資料請求については.>>こちら