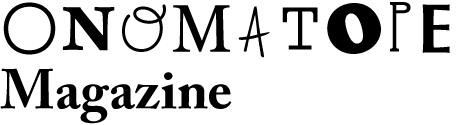2015年9/12(土)に総合領域主催のUX SHIGA 第二回目が開催されました。
講師に浅野 智先生(UXコンサルタント・研究者)をお招きいたしました。
今回は「オブザベーション(観察法)ワークショップ」を行いました。
まず、質的調査に関する講義を受け、実際にグループワークでオブザーベーション(観察法)を実践しました。
調査には量的調査と質的調査がありますが、今回は質的調査の中でも対象社会の生活の直接観察を行いました。(人間が観察対象を直接観察することを直接観察、ビデオやセンサーを通しておこなうことを間接観察といいます。)
直接観察のメリットは、人間が観察や判断をおこなうので情報量を多く得られることです
講義の後のワークショップでは、被験者をひとり決定しゼリーを食べてもらいます。そのほかのグループメンバーは行動記録、発話記録、撮影係、モデレータを担当します。モデレーターは被験者の発言などが滞った際に、スムーズに観察を進めるための司会者のような役割です。
実際にゼリーを食べる被験者にはゼリーをたべながら思ったことをすべて発話してもらいます(思考発話法)。
そして被験者の行動と発話を細かく記入することで分析がしやすくなります。動作一つ一つまで注意深く観察することによって問題点や優れている点がたくさん見えてきます。観察の際に注意したいことは、ゼリーやパッケージを観察するのではなく、ゼリーを食べている「人」を観察するということです。
観察が終わった後、この記録を見ながらグループ内で、エラー・気になること・変わった行動などの外的事象を加えていきます。被験時の動画なども見返しながら見落とした情報を補ったりします。
情報が出揃ったところで、つぎの ステップ:上位下位位置関係分析法に進みます。
作業ステップと観察した事象(行動や発話)をふせんに書き出していきます。
ゼリーを食べた被験者が3人おり、三者三様の行動・発話があるのでたくさんのふせんが貼られました。
この具体的な事象のなかから、問題点やエラーをみつけだし、グループの中で話し合い改善案を提案していきます。
発話のなかに問題点が潜んでいる事もあるので、しっかりと情報を選びながら思考する必要がある作業です。
初体験の参加者も多く、手探りながらも表の完成を目指し取り組んでいました。
最後に作業ステップの時系列に沿って被験者の心理曲線を描きます。
プラスの感情が働いたときとマイナスの感情が働いたときをグラフ化することによって、
感情が平均的に似ている部分や個人差が激しい部分など問題点と照らし合わせて改善案のヒントにします。
あらためて自分の気持ちを見える化(グラフ)にすることの難しさを感じている参加者も多かったです。
最後に各チームでプレゼンを行いました。
問題点の抽出に時間がかかりすぎてプレゼンテーションの準備が充分でないチームも見受けられました。
手探り状態からはじまったワークショップでしたが、次回へつなげるための改善案は見つかったように思います。
全チームのプレゼンも終了し、次回の講義に向けたお話がありました。
次回は、ペルソナ(商品などの対象者を詳細に記述した人物像)とシナリオを作成し、今回のオブザベーションの結果として得られた改善案のヒントをもとに、新たなゼリーのパッケージを企画する予定です。
毎回、講義とワークショップのあとに懇談会が行われています。
ビアバッシュという形式でおこないます。ビアバッシュとは、使用した会場でピザをたべながらビールをのみ、振り返りも兼ねて歓談するものです。
初回ではすこし参加者の緊張などを感じましたが、今回は二回目という事もあり意見の交換が盛んに行われていたように思います。
その後、情報デザイン研究会のメンバーが遅くまで反省会を行っていました。
確実に一歩づつ学びを深めている様子がみられ、今後どのように学生の中で発展していくのかとても楽しみです。
次回のUX SHIGA は10/12(月)に行います。