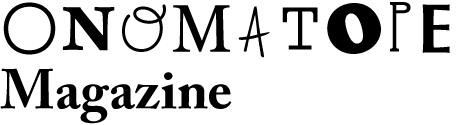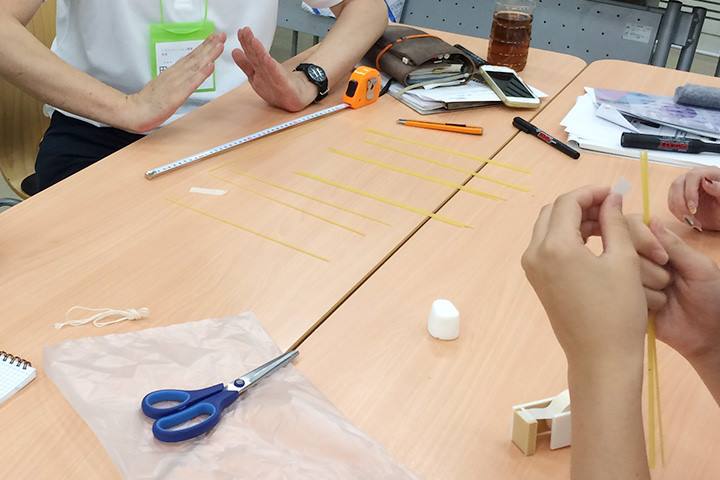2015年8/29(土)に総合領域主催のUX SHIGA 第一回目が開催されました。
講師に浅野 智先生(UXコンサルタント・研究者)をお招きいたしました。
UX概論・ミニワークショップ・チームビルディング
UX概論の講義(前編)では、「学ぶということはどういうことか」、「体験を経験に昇華するにはどうしたら良いのか」、「グループでの学習はどういう点が有効なのか」、「スキル学習と発達の違い」などについてお話いただきました。
休憩をはさんでの講義(後編)では、「UXを生み出すためのアプローチとしてのHCD(Human Centered Design:人間中心設計)」とその根幹をなす「質的調査」の意義について、アンケートやビッグデータによる「量的調査」との違いにも触れながら、具体的な事例を挙げてご説明いただきました。「質的調査」は次回以降のワークショップで少しずつ体験していきます。

講義の様子は情報デザイン研究会の学生たちがグラフィックレコーディング。講義の合間にはグラレコに対する重要なアドバイスもいただきました。
経験デザインWSでは、「モノからの発想」と「コトからの発想」の違いを個人ワークで体感。1枚目と3枚目で出来上がったデザインの違い。両方とも自分で描いたものだからこそ、2枚目のワークの必要性を「なるほど!」って実感できたのではないでしょうか?

チームビルディングワークショップでは、マシュマロチャレンジを体験。
グループ学習やワークショップの心得として「他チームの進行を見に行ってヒントを得ることも重要」とのアドバイスを事前に受けていたのにも関わらず、「短時間で結果をださなくては」との思いが強くてなかなかそれを実行できていませんでした。結果、マシュマロ位置を計測できたのは2チームのみ。
今回は省略しましたが、ここからもう一度チャレンジすると良いチームビルディングができるのだそうです。
ワークショップでの具体的な「体験」を「経験」として修得するには、講義(前編)で紹介されたデビッド・コルブの「経験学習理論」を実践する必要があります。まず大切なのは「体験を振り返る:どんな体験をしたのか、そこで何が起こって、何を感じ、何を考えたのか、他の人はどうやっていたのか・・・」。次にそれを「抽象的に概念化:なぜそうなったのか、同じような場合にどうすれば良いのか、その体験から何を得たのか、などを個別の体験としてではなく、他にも応用できる形で一般化して整理しておく」します。そうすることによって、それまでの「経験」に新しい「体験」が積み重なり「経験」がバージョンアップされるのです。
ワークショップに参加した方は、どうぞブログなどでその体験を振り返って、概念化してみてください。
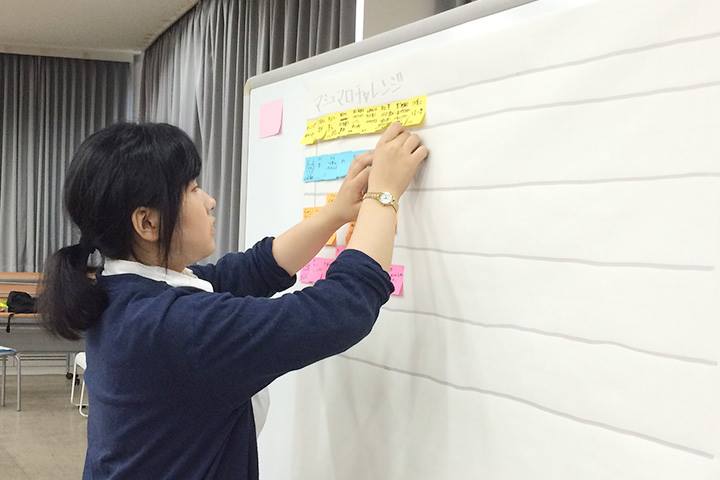
第2回 9月12日(土)は、『オブザベーションとプロトタイピング』です。
この記事はUX SHIGAのフェイスブックページを修正、引用しています。
https://www.facebook.com/UX.SHIGA/posts/1621293848120225