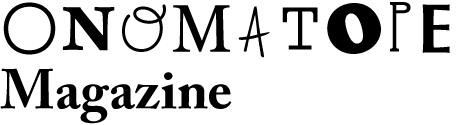総合領域4年生の特別講義「コト・モノ・情報についてデザインする」の今年度の2回目が、2018年5月15日に行われました。
今回は、スタジオカルティベイトのデザインプロデューサーの相原幸雄先生とフードコーディネーターの藤本紀久子先生をお招きし、「フードとデザインの関係性の考察」をテーマに講義していただきました。

前半では藤本先生の活動の一つとして、シーズンディレクションのお話を伺いました。
藤本先生は、長年にわたり松屋銀座のシンクタンク 東京生活研究所のフードコーディネーターとして活躍されていますが、その中の主なお仕事がシーズンディレクション。
1年を6つのシーズンに区切り、さまざまな分野のトレンド分析をベースに、人々が生活全体の中でどのように食をとらえ、それぞれの季節でどう楽しむのか「食」の消費動向を予測していく、百貨店全体のマーチャンダイジング戦略を牽引していく非常に重要なものです。
人々は単に「食べもの」を買うのではなく、それにまつわる「空気」や「文化背景」を買うのだ、という言葉がとても印象的でした。

後半の相原先生の講義では、さまざまな老舗に対し新たなデザイン戦略を提案しブランド性を作り上げていかれた事例を、数多くのエピソードを交えながら語っていただきました。
地方創世や地域活性化のテーマのもと地方で活動するプロデューサーやデザイナーが注目されています。その中でも地域の「食」の特産物は私たちにも身近なものです。
酒蔵や和菓子店など「食」の作り手たちが自分では気づいていない価値を、相原先生が見出し、物語性あるデザインや言葉をそこに与えるなかで、ブランド性を生み出し、店の幹として育てていかれました。はじめはデザインに懐疑的なクライアントたちも、最後には誇りを持って「食」を作り、店や町の賑わいを生むにいたる、デザインの力の可能性を感じるお話でした。
相原先生がクライアントに寄り添いながら、ともにブランドを育て上げる姿勢は、総合領域の学びに通ずるものが大きく、学生たちにとっても非常に刺激にある内容ばかりでした!

相原先生、藤本先生、本当にありがとうございました!
下記はスタジオカルティベイトが携われた食品ブランドの一例。